【小学生】学校の成績を効率的に上げる方法
こんにちは、イガヤス です。
子どもの『学校の成績がなかなか上がらない』といった悩みは、ずっと付きまといますよね。
「宿題ちゃんとやっているけど、テストの点数がイマイチ上がらないなぁ」
「公文行ってるけど、成績が変わらない。。。効果あるの?」
などと思ったことはありませんか?
そんな人にオススメしたいのが、『学校の成績を効率的に、戦略的に上げる方法』です。
私もこの悩みを抱えていました。ですが、ポイントを絞って対策を打ったところ、次の学期には、かなり成績を上げることができたのです。
自発的・主体的に勉強することの大切さ
これは評論家、文筆家として活躍する岡田斗司夫さんと、教育心理学などを研究する心理学者の安藤寿康さんの対談動画なんですが、
「子どもの能力は、ある程度遺伝で決まっている。だが、訓練(自発的・主体的に何かを行うこと)によって、遺伝を凌ぐ効果を発揮するかもしれない」
ということが語られていました。
クラスに一人か二人、勉強しなくてもテストの点数が良い子っていませんでしたか? その子たちは遺伝的に勉強ができる能力を持っているのでしょう。
でも、「自分から進んで勉強する子」であれば、その子たちより成績をもっと上げることができるかもしれません。
通知表のつけ方の実態
みなさん、小学校の通知表はどのようにつけられているかご存知ですか? 実際はどのようなことになっているのでしょうか・・・。
これは、元小学校教員の方が学校の成績のつけ方について語っている動画です。かなりわかりやすく説明してくれています。
この動画の一番のポイントは、「学校の成績は文科省の規定に準じてつけられているけれど、基本的に現場の先生の裁量に任されている」という点です。
ということは、「先生によって成績のつけ方が異なる」・・・ということで、例えばですが、いくらテストの点数をUPさせたとしても、必ずしも通知表の「よくできる」に○が増えるわけではない・・・ということなんです。
学校や学年によっても成績の付け方のポイントは違います。ですので、成績の指針は非常にわかりにくいのが現状のようです。
なぜ学校の成績が上がらないのか?
イラスト
いやいや勉強をやっている
私の子どもは、1年生から「よくできる」の○がなかなか増えず、鳴かず飛ばずでした。ですが、2年生の3学期になって、いきなり○が増えたのです。
一番大きかった理由は、子どもが自ら私立小学校の編入試験を受けることを決め、「自発的に勉強したこと」だと考えています。そういう目標を持ったことが、自ら勉強しようという気持ちを促したと感じています。
宿題一つにしても、自分から宿題を一生懸命やっている子どもと、イヤイヤやっている子どもとでは効果が全然違うと感じました。
子どもが自ら学ぼうという意志をもって勉強しなければ、ある程度の成績はキープできたとしても、クラスの平均点から頭一つ出るのはなかなか難しいのかもしれません・・・。
学校の成績が芳しくないようであれば、「主体的に勉強する」といったお子さんの意識改革が必要だと思います。
成績の付け方の指針をわかっていない
前述しましたが、先生によって成績の付け方は違います。担任の先生の傾向を分析することが必要です。
私の子どもの先生の場合、いくら見取り(授業態度や発言力、提出物の評価)が良くても、テストの点数が90点以上でないと、「よくできる」の○は増えませんした・・・。なので、見取りはしっかりキープしつつ、宿題以外に問題集などで勉強し、テストの点数を上げるようにしました。
傾向がわからないと、勉強しているわりには成績が上がらないといった負の連鎖に陥りかねません。
お子さんのテストの点数と見取りを比べつつ、先生がどのように成績をつけているか分析しましょう。
1学期の結果を分析して、そこで対策を練り、2学期・3学期で、どこに力を入れたらよいかを考えます。分析すれば、なんとなくの傾向はわかると思います。また、1学期の先生との個人面談で、どこをポイントに成績をつけているか質問してみるのもよいかもしれません。
自発的・主体的に勉強するためには?
イラスト
自分から勉強させるって難しいですよね・・・。TV、ゲーム、漫画など、子どもの周りには誘惑もいっぱいです。どうしたら、そういう気持ちになるのか、その方法をご紹介します。
目標を立てる
目標を立てることをお勧めします。私の子どもの場合は、「私立小学校の編入試験に合格する」でした。
例えば、「算数検定○級に合格する」、「漢字のテストは毎回100点を取る」など、目標はお子さんと相談しながら決めると良いと思います。
但し、あまり遠い目標ですと、成功がうまくイメージできず、逆にやる気が失せてしまう可能性があります。努力しても突破できなさそうな目標ではなく、最初は敷居の低い目標にすることがポイントです。また、いつ達成するかなど、スケジュール感も共有しましょう。
成功体験するこそが、自ら勉強を進んで行う第一歩です。
- 初めに敷居の低い目標を立てよう
- いつ目標を達成するのか、スケジュール感を共有しよう
目標を達成した過程を褒める
これは、いろんな方が言われていることだと思います。
目標を達成したことを褒めるというよりも、その過程を褒めましょう。
例えばテストで100点を取ったとします。そこで結果だけ褒めてしまうと、100点を取らないとダメなんだといった誤解を生み、次に100点が取れないと、勉強のやる気が一気に失せてしまいます。例え結果が良くなかったとしても、努力したことを褒めてあげれば、またがんばろうという気持ちになります。
以下は、褒め言葉の一例です。
- 自分から勉強したから、目標が達成できたんだよ
- 今まで努力した結果だね、コツコツやることって大切だね
- 今回は残念だったけど、日々努力してれば、いずれ良い結果が出るから続けていこう
尚、目標を達成した後のご褒美は禁物です。一時的な意欲の向上にはなっても、中長期的に効果はありません。ご褒美をやめた途端、やらなくなってしまうことも・・・。
目標を達成すると、将来、お子さん本人がやりたいことの選択肢を増やすことができます。なかなかすぐ理解してくれないかもしれませんが、このことをしつこく言い続けましょう。
また、努力をした後のテストの答案用紙や検定の証明書などは、家族が集まるところに貼っておきます。本人の意識の確認にもなりますし、家族が応援してくれているという証明になり、励みになります。
- 結果ではなく、努力した過程を褒める
- 目標を達成した後のご褒美は禁物
- 努力をした後の結果は、家族が集まるところに貼っておく
1日1回、勉強を習慣化する
これは学校の先生もよく話されていることだと思います。
宿題があるので、平日は机に向かう機会があるかと思いますが、宿題のない日や土日の休日も続けてください。
勉強はトレーニングです。毎日勉強すれば、必ず結果がついてきます。また、自分の努力と良い結果が結びつく経験をすると、過程の大切さを学びます。そのうちに机へ向かう気持ちも培われていきます。
宿題のない日はたった1分でも大丈夫です。簡単な計算問題2、3問や、音読でも構いません。大事なことは1日1回机の前に座り、勉強する機会を作り、それを習慣化することです。
だけど、これってほんとにとっても難しいですよね。。。
特に休日・・・。休日はダラダラしたいし、夜まで出かけていることもあります。
私も本当に苦労しました。でも、これを習慣化すると、いくらダラダラしていても気持ちの切替ができていきます。
1回でもサボると、「やんなくてもいいんだ」と思われ、次の日から「やりたくない!」と言ってきたりするので、余程のことがない限り、がんばって続けてみましょう。
うちの子どもは何ヶ月か経ったある日の休日に、「今日の勉強は算数の応用問題をやってみる!」と宣言してきました。
目標を掲げて、お子さんのやる気を何とか掘り起こしてみましょう。
- 勉強は1日1回必ずやって習慣化する
- 宿題のない日や土日も必ず勉強する
成績を上げる対策・作戦を立てる
イラスト
子どもをやる気にはさせたけど、じゃあ具体的にどういう勉強をしたらいいの?
ということで、ここからは効率的な勉強法を詳しくお伝えしていきます。



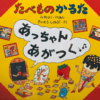

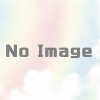



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません